
���S�q���̃L�[���[�h�ŊS���������̂ɂ��ĉ�����Ă��܂��B
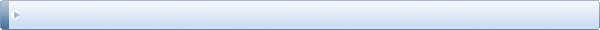
�d���t�@���t���ċz�p�ی��iPowered Air Purifying Respirators�A�ȉ��uPAPR�F�s�[�G�[�s�[�A�[���v�Ƃ����B�j�́A���p����J���҂̎��ӂ̍�Ɗ����̋�C����߂��Đ���ɂ�����C����������u��ߎ��ċz�p�ی��v�̈��ŁA��C���̗��q�i������j���t�B���^�ɂ���ď������A�d���t�@���ƃo�b�e���[���g�p���Ē��p�҂ɑ������邽�߁A�����̔x�ŋ�C���z������h����}�X�N��h�Ń}�X�N���y�Ɍċz���ł��A���p�҂̌ċz�p�C���^�t�F�[�X�̓������O�C����荂���ۂ����i�z���j���ߊO�C�̘R�ꂪ���Ȃ��A�h�엦���\�̍����ċz�p�ی��̂��Ƃł��B�i�z�C�⏕��t���h����}�X�N�i�^�����荇�i�W�͂Ɂu��v�̃}�[�N�j���o�b�e���[�Ƃ���ɂ���ċ쓮����t�@�����g�p���Ē��p�҂ɑ�������@�\��L���Ă���܂����A��ɗz�����ۂ������̂ł͂Ȃ����Ƃ���PAPR�ɂ͊܂܂�܂���B�j �d���t�@���t���ċz�p�ی��ɂ́A�@�h����@�\��L����d���t�@���t���ċz�p�ی��iP-PAPR�j�ƇA�h�ŋ@�\��L����d���t�@���t���ċz�p�ی��iG-PAPR�j������܂��B�������݂�����ł�P-PAPR��I�����A�L�ŃK�X�����݂�����ł�G-PAPR��I�����A�L�ŃK�X�ƕ������݂�����ł�G-PAPR�Ŗh����@�\��L������̂�I�����܂��B
PAPR�́A�h����}�X�N��h�Ń}�X�N�Ɣ��ʓI�ɖh�쐫�\�������A�J���҂̌��N��Q�h�~�̊ϓ_������L�p�ł��邽�߁A���p���`���t�����Ă������̍�ƈȊO�̍�Ƃɂ����Ă�PAPR�𒅗p���邱�Ƃ��]�܂�܂��B
PAPR�ɂ͎_�f����������\�͂͂���܂���̂ŁA�_�f���R���i�_�f�Z�x18%�����j�ł͎w��h��W����1000�ȏ�̑S�ʌ`�ʑ̂�L���鋋�C���̌ċz�p�ی��i���p�҂��A���ӂ̍�Ɗ����̋�C�Ƃ͕ʂ̋�C�A�_�f���͌ċz�\�ȃK�X���ċz��������̌ċz�p�ی��j���g�p���Ă��������B
PAPR�ɂ��ẮA�J�����S�q���@��42�� �Ɋ�Â��W�@�߂̉����̂ق��A�u�d���t�@���t���ċz�p�ی��̋K�i�v
�Ɋ�Â��W�@�߂̉����̂ق��A�u�d���t�@���t���ċz�p�ی��̋K�i�v
 �i����26�N11��28���@�����J���ȍ�����455���j����������i�ߘa5�N�����J���ȍ�����88���j�AP-PAPR�ɉ����A�ߘa5�N10��1������G�|PAPR�����n�������̑ΏۂƂȂ�A�^�����肪�`���t�����܂����B���ƌ���i�^������j�ɍ��i����PAPR���g�p���Ă��������B
�i����26�N11��28���@�����J���ȍ�����455���j����������i�ߘa5�N�����J���ȍ�����88���j�AP-PAPR�ɉ����A�ߘa5�N10��1������G�|PAPR�����n�������̑ΏۂƂȂ�A�^�����肪�`���t�����܂����B���ƌ���i�^������j�ɍ��i����PAPR���g�p���Ă��������B
���Ǝ҂́A�J���҂ɗL���Ȍċz�p�ی����g�p�����邽�߁A���̑[�u���u����K�v������܂��B
���S�q���L�[���[�h�u�ی��p�Ǘ��ӔC�ҁv���Q�Ƃ̂��ƁB
�J�����S�q���K�����̈ꕔ����������ȗ߁i�ߘa�S�N�����J���ȗߑ�91���j�ɂ�������̘J�����S�q���K���i���a47�N�J���ȗߑ�32���B�ȉ��u���q���v�Ƃ����B�j��577���̂Q��P���ɂ����āA���Ǝ҂ɑ��A���X�N�A�Z�X�����g�̌��ʓ��Ɋ�Â��A��֕��̎g�p�A���U���𖧕���ݔ��A�Ǐ��r�C���u���͑S�̊��C���u�̐ݒu�y�щғ��A��Ƃ̕��@�̉��P�A�L���Ȍċz�p�ی����g�p�����邱�Ɠ��K�v�ȑ[�u���u���邱�Ƃɂ��A���X�N�A�Z�X�����g�Ώە��ɘJ���҂����I�������x���ŏ����x�ɂ��邱�Ƃ��`���t����ꂽ�B����ɁA�����Q���ɂ����āA�����J����b����߂���̂����A���͎�舵���Ɩ����s��������Ə�ɂ����ẮA�J���҂������̕��ɂ��I�������x���A�����J����b����߂�Z�x�̊�i�ȉ��u�Z�x��l�v�Ƃ����B�j�ȉ��Ƃ��邱�Ƃ����Ǝ҂ɋ`���t�����܂����B
�����܂��A���w�����ɂ�錒�N��Q�h�~�̂��߂̔Z�x�̊�̓K�p���Ɋւ���Z�p��̎w�j�i�ߘa�T�N�S��27���t���Z�p��̎w�j������24���B�ȉ��u�Z�p��̎w�j�v�Ƃ����B�j����߂��A���w�������ɂ��댯�����͗L�Q�����̒������Ɋւ���w�j�i���� 27 �N�X�� 18 ���t���댯�����͗L�Q�����̒������Ɋւ���w�j������R���B�ȉ��u���w�������X�N�A�Z�X�����g�w�j�v�Ƃ����B�j�Ƒ��܂��āA���X�N�A�Z�X�����g�y�т��̌��ʂɊ�Â����X�N�ጸ�[�u�Ƃ��Čċz�p�ی����g�p����ꍇ�ɁA���̓K�ȑI���A�g�p�A�ێ�Ǘ����ɓ������ė��ӂ��ׂ������Ƃ��āA�u�h����}�X�N�A�h�Ń}�X�N�y�ѓd���t�@���t���ċz�p�ی��̑I���A�g�p���ɂ��āv�i�ߘa5�N5��25���t���0525��3���j��������܂����B���̒ʒB�ɏڍׂ��L�ڂ���Ă��܂��̂ŁA�����ł͊�{�I�ȍl�����������܂��B
(1)���Ǝ҂́A���w�������X�N�A�Z�X�����g�w�j�ɋK�肳��Ă���悤�ɁA�댯�����͗L�Q���̒Ⴂ�����ւ̑�ցA�H�w�I��A�Ǘ��I��A�L���ȕی��̎g�p�Ƃ����D�揇�ʂɏ]���A����������A�J���҂̂��I�̒��x��Z�x��l�ȉ��Ƃ��邱�Ƃ��܂߂����X�N�ጸ�[�u�����{���邱�ƁB���̍ہA�ی��ɂ��ẮA�K�ɑI������A�g�p����Ȃ���Ό��ʂ����Ȃ����Ƃ܂��A�{�����S���A�H�w�I�����̐M�����Ɣ�r���A�ł��Ⴂ�D�揇�ʂ��ݒ肳��Ă��邱�Ƃɗ��ӂ��邱�ƁB
(2)���Ǝ҂́A�J���҂̌ċz��ɂ����镨���̔Z�x���A�ی��̎g�p���������X�N�ጸ�[�u���u���Ă��Ȃ��A���Y�����̔Z�x��l���邱�Ɠ��A���X�N�������ꍇ�A�L���Ȍċz�p�ی���I�����A�J���҂ɓK�Ɏg�p�����邱�ƁB���̍ہA���Ǝ҂́A�ċz�p�ی��̑I���y�юg�p���K�Ɏ��{����Ȃ���A�����̐��\����������Ȃ����Ƃɗ��ӂ��A�ċz�p�ی��K�ɑI���y�юg�p����Ă��邩�̊m�F���s�����ƁB