水道のポンプ場の受変電設備で地絡アークを浴びる
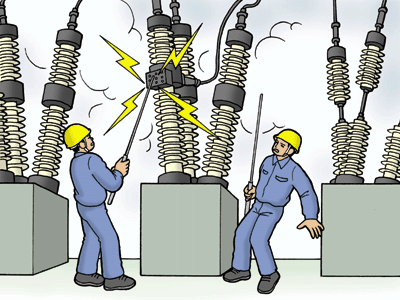
| 業種 | 水道業 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業場規模 | 30〜99人 | |||||
| 機械設備・有害物質の種類(起因物) | 電力設備 | |||||
| 災害の種類(事故の型) | 感電 | |||||
| 被害者数 |
|
|||||
| 発生要因(物) | ||||||
| 発生要因(人) | ||||||
| 発生要因(管理) | ||||||
No.100648
発生状況
この災害は、地方公共団体の水道のポンプ場で発生したものである。このポンプ場は、大規模の浄水池および幹線に上水を供給求するために設置されているが、無人でその運転は別の場所にある送水管理センターでコントロールしている。
災害発生当日、このポンプ場では、電力会社より供給を受けている77,000Vの受電設備の切り替え工事が予定され、電力会社から2名と地方公共団体本部から保全担当の主査と電気技師の2名が出張してきて、午前10頃から2階操作室で2号線から1号線への切り替えを空気遮断器で行い、午前10時20分に切り替え作業は終了した。
その後、電力会社の2名は検針、メーターの取替えを行ってポンプ場を退出したが、その直後に送水管理センターから空気遮断器操作用の空気源の圧力が低下して警報が鳴っているとの連絡が入ったので、本部からきていた2名が原因調査に向かった。
午前10時51分に、送水管理センターで地絡警報が出され、同時に電力会社の送電も停止された。
一方、1階ポンプの点検に入っていた他の会社の作業員2名は、午前10時50分頃に停電があり照明も消えたので、2階の操作室に確認に行ったところ、すべての電源が切れていた。
そこで、原因を探していたところ、2号受電室の扉が開いていて煙が充満しているのが見えたが、室内に入るのは危険なので屈んで中を見ると、うめき声が聞こえたので直ぐに2階の操作室に戻り、送水管理センターに連絡するとともに、救急車の手配をし、送電が再開されると危険なので受電設備の電路を遮断した。
午前11時09分に、救急車、消防車、警察官が到着し救出に向かったところ、電気技師が自力で脱出してきたが、主査は衣服が燃えていて即死の状態であった。なお、電気技師は火傷により3か月の休業となった。
原因
この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。| 1 | 特別高圧電路に接近しすぎたこと 被災した2名は、送水管理センターから空気遮断器の操作用空気源に異常があることの連絡を受けてから、2階の操作室に行き空気圧の異常を確認し、建物の各室の鍵を持って異常個所と原因を特定するため、3階の2号受電室の扉を午前10時50分(扉開放の時間は、送水管理センターで確認されている)に開けて同じ階にある圧縮空気発生装置室に向かったものと推定される。(休業となった被災者は、前後の記憶があいまい) このときに、受電を切り替えたばかりの特別高圧電路の充電部に接近しすぎて、地絡事故となってアークを浴びたものと推定される。 |
|
| 2 | 緊急時の作業要領が明確でなかったこと 被災した2名は、送水管理センターから連絡を受けて直ちに原因特定のための行動を起こし、結果的に最短の危険な箇所を通り抜けようとして被災したものと推定されるが、このような異常の場合の回復作業要領(チェック順路、送水管理センターとの連絡要領、停電の確認要領、必要な装備等)が定められていなかった。 |
|
| 3 | 電撃危険についての認識が不十分であったこと 被災した2名は、電気関係の技術者として採用され、その後継続して電気関係の作業に従事するとともに、電気に関する特別教育も受けてはいたが、緊急的な事態に遭遇したときに電撃危険のある受電室であることを忘れていたものと推定される。 |
|
対策
同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。| 1 | 非定常作業における手順を定め教育訓練を実施すること この災害のようにトラブル解消のための作業等(いわゆる非定常作業)では、異常事態の回復に意識が先走り、作業に伴う危険有害性を忘却することが少なくないので、想定されるトラブル等について摘出し、あらかじめ基本的な作業手順を定めて教育訓練を実施する。 また、作業行動の要所において「指差し呼称」や「一人KY」を取り入れることが効果的であるので、教育訓練の中に組み込むことが望ましい。 |
|
| 2 | 接近限界距離の表示等を明確に行うこと 特別高圧電路等では近接ことによる電撃危険のおそれが大きいので、電圧に応じた接近限界距離を明確に表示するとともに、囲い等により接近ができないような措置を行う。 また、このような場所には、一定の知識経験を有する者だけが立ち入ることが原則であり、緊急の場合であっても通路として使用することのないよう表示や鍵の管理を十分に行う。(安衛則第344,345条関連) |
|
| 3 | 能力向上教育を実施すること 充電電路の取扱または支持物の敷設、点検、修理、操作の業務等については、一定のカリキュラムによって特別教育を受けた者が従事することになっているが、教育を修了した者についても定期あるいは随時に能力向上のための教育(いわゆる再教育)を実施する。(安衛法第19条の2、安衛則第36条関連) |
|
 厚生労働省
厚生労働省