大規模小売店舗の受変電設備の清掃中に電気火傷
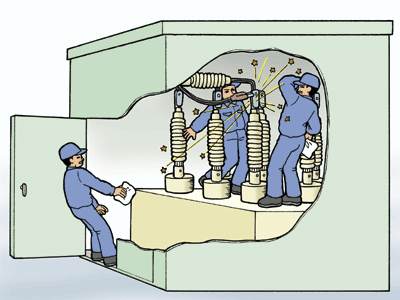
| 業種 | ビルメンテナンス業 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業場規模 | 100〜299人 | |||||
| 機械設備・有害物質の種類(起因物) | 電力設備 | |||||
| 災害の種類(事故の型) | 感電 | |||||
| 被害者数 |
|
|||||
| 発生要因(物) | ||||||
| 発生要因(人) | ||||||
| 発生要因(管理) | ||||||
No.100637
発生状況
この災害は、大規模小売店舗の地下受変電設備の清掃中に発生したものである。被災者の所属する会社は、大規模小売店舗の系列会社で全国に事業場を置いてビルメンテナンスの業務を行っている。
災害発生当日は、ある店舗の地下受変電設備の年次点検に当たっていたので、店舗に常駐するチーフ(被災者)および被災者AおよびBの3名は、午前8時に店舗ビル屋上の詰め所に集まって当日の作業の打ち合わせを行い、その後、チーフが点検業務の一部を請け負わせた会社の作業者への指示、電力会社の変電所への電話による停電依頼、DS(断路器)操作を行って作業に着手した。
作業は、まず地下の特別高圧受電設備の碍子を掃除する準備として、3名で非常用バッテリー電源の取り付け、投光器の設置を行い、その後2L系統の碍子をウエスで拭く作業を行った。
正午から1時間の休憩を取り、午後は3階電気室にある碍子の清掃を行おうとしたが、外注した業者がすでに終了していたので、地下の1L系統の清掃を行うことに変更し、被災者Aがキュービクルの正面扉およびその内側の覆いパネルを開け、被災者Aとチーフが脚立を利用してキュービクルの下部にあるコンプレッサーのフレームに上がり碍子の清掃を始め、被災者Bはキュービクルの外側から碍子の清掃を行った。
午後1時30分頃、被災者Aが店舗側ケーブルのC相の設備とキュービクル壁との間、チーフがA相の設備とキュービクル壁との間、被災者BがA相の設備の外側で碍子の清掃を行っていて、被災者Aがコンプレッサー上から立ち上がって身体を奥に入れた瞬間、C相で地絡が生じDSからアークを発し、続いてB相とC相との間で相間アーク放電が発生した。
これらのアーク放電により3名は火傷を負い、救急車で病院に移送されたが、被災者Aは全身重症熱傷のため翌日に死亡し、チーフが2か月、被災者Bが5日の休業となった。
原因
この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。| 1 | 作業箇所の変電所側は通電されていたこと 3名が被災した直接の原因は放電アークを浴びたことによる熱傷であるが、被災者らが碍子の清掃を行っていた1L系統の受電設備の店舗側はDSが開放されていて停電状態であったものの、電力会社の変電所側は通電状態(33,000V)であったため、被災者Aがコンプレッサーから立ち上がって通電側に身体を入れたときに、充電部に接近しすぎて地絡放電が発生したものと推定される。 また、この地絡放電が引き金となって相間放電が発生し、近くにいた他の2名も熱傷を負ったものと推定される。 |
| 2 | 作業計画と異なる作業を実施したこと 当初の作業計画では、1L系統の碍子の清掃は、午後2時以降に停電とした上で実施する予定となっており、午後2時から5時までは電力会社側の変電所で停電することになっていた。 しかし、午後から最初に実施予定の3階電気室の碍子清掃作業は、外注した会社の作業員によってすでに終了していたので、作業計画を急遽変更して地下室に戻り1L系統の碍子清掃に取り掛かったものであるが、その際にキュービクル内の通電、停電の状況を確認しなかった。 |
| 3 | アーク放電による危険の認識がなかったこと 災害の発生した店舗の電気設備の電気主任技術者は、被災者Aであったが実質業務は行わずチーフがその職務を行っていた。 しかし、両者とも特別高圧電路へ接近することによる危険についてはほとんど意識していなかった。 |
対策
同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。| 1 | 作業計画を変更する場合はあらためて安全性の確認を行うこと 特別高圧電路に近接して作業を行う場合には、あらかじめ十分に検討した安全な作業計画を定めるとともに、作業の指揮者を定めて次のことを実施させる。(安衛則第350条関連) |
||
| (1) | 労働者にあらかじめ作業の方法および順序を周知させ、かつ、作業を直接指揮すること | ||
| (2) | 接近限界距離を標識等で明示するか監視人を置くこと | ||
| (3) | 電路を開路して行うときは、その回路の停電の状態、開閉器の施錠、通電禁止の表示、監視人の配置、短絡接地器具の取り付け状態等を確認のうえ作業の着手を指示すること | ||
| なお、作業計画を変更して作業を行う場合には、あらためて上記事項の確認を行う。 | |||
| 2 | 特別高圧電路に近接して作業を行う場合の危害防止措置を行うこと 特別高圧電路に近接して電路またはその支持物の点検、修理、塗装、清掃等の作業を行わせる場合には、労働者に活線作業用装置を使用させること、充電電路への接近限界距離を保たせること(接近限界距離を標識等で明示するか監視人を置くこと)等の危害防止措置を確実に行う。(安衛則第345条関連) |
||
| 3 | 電撃危険について十分に教育を行うこと 事業者は、電気主任技術者等の資格を有する者についても電撃危険(放電による危険を含む)について、あらかじめ十分な安全教育を実施する。 なお、充電電路またはその支持物の点検、修理、塗装、清掃等の作業に従事する者に対しては、あらかじめ一定のカリキュラムによる特別教育を実施する必要があるが、充電電路に近接して作業を行う者に対しても同種の教育を実施しておくことが望ましい。(安衛則第36条関連) |
||
 厚生労働省
厚生労働省