橋脚下部工深礎杭建設工事中、立坑内部のフープ筋を伝って坑底まで降りようとして墜落
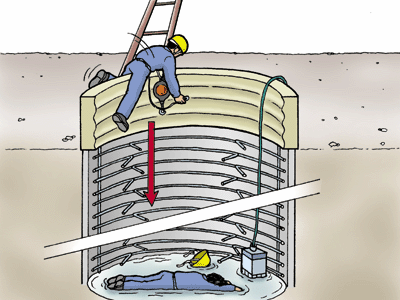
| 業種 | 橋梁建設工事業 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業場規模 | 1〜4人 | |||||
| 機械設備・有害物質の種類(起因物) | 建築物、構築物 | |||||
| 災害の種類(事故の型) | 墜落、転落 | |||||
| 建設業のみ | 工事の種類 | 橋梁建設工事 | ||||
| 災害の種類 | 坑、ピットへ墜落 | |||||
| 被害者数 |
|
|||||
| 発生要因(物) | 整備不良 | |||||
| 発生要因(人) | 無意識行動 | |||||
| 発生要因(管理) | 保護具を使用していない | |||||
No.100611
発生状況
この災害は、道路橋脚深礎杭建設工事において、立坑壁の配筋作業中に発生したものである。災害発生当日の作業は、移動式クレ−ンで径22mmの段取筋6本を入れて坑壁の周り垂直方向に立て、坑口付近と深さ11mの立坑の底付近の2箇所のアンカ−に固定し、フ−プ筋を立坑の中に入れ、底から高さ1.7mまで段取筋に取付けた。この後、立坑の中に1.7mの高さまで枠組足場を組立て、立坑の中へ主筋を吊り入れ、この足場を利用して主筋をフ−プ筋に取付ける作業を行った。なお、この作業の後、枠組み足場は一旦解体され、取り除かれた。
昼休みの休憩中に現場代理人から午後の作業の段取りの説明があり、立坑の中の水中ポンプを真ん中に移動させることと次の主筋組立ての準備を行うことになった。
そこで、立坑へ長さ5.5mの主筋20本と長さ9.5mの主筋20本を吊り入れた後、被災者が立坑の底に設置した水中ポンプの位置の移設のため、立坑のフ−プ筋を昇降設備替わりに足を掛け、降りようとして立坑の中へ入り、足を滑らせて立坑の底へ墜落した。
坑口には昇降時に使用するセフティブロックが設置されて、被災者の腰には安全帯が装着されていたが、被災者は、これらを使用していなかったため、立坑の底まで墜落した。
原因
この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。| 1 | 深さ11mの立坑内部との昇降で、安全な昇降設備を設けることを省略し、立坑内壁の周囲に沿って約15cm間隔で結束された直径29mmのフ−プ筋を昇降の足がかりとして昇降設備替わりに使用していたこと |
| 2 | 立坑内部に入る前に昇降の際の補助安全器具として使用することになっていたセフティブロックを安全帯に引っ掛けないで降りた作業者の不安全行動があったこと |
| 3 | 立坑内での主筋組み立て作業が全て終了するまで、立坑内に設置した枠組み足場を解体する必要がなかったにもかかわらず、作業の途中に一旦解体し、再度組立てて昇降設備とするという作業手順を採用していたため、昇降設備が存在しない状態で昇降しなければならない状況になってしまったこと) |
| 4 | KY活動の内容がおざなりで、作業内容に適応したものとなっていなかったこと また、作業員への安全教育が不徹底であったこと |
| 5 | 作業計画が不適切であり、作業打ち合わせも不十分であったこと |
対策
同種災害の防止のためには次のような対策の徹底が必要である。| 1 | 立坑内に設置した枠組み足場については、立坑内での作業が全て終了したとき、これを解体するという作業手順に改め、作業の途中で昇降設備が存在しない状態とならないよう作業計画を作成すること |
| 2 | KY活動を作業内容に応じた的確なものとし、事業者は、これが遵守されていることを確認するとともに、作業者には指示事項の確実な履行を図るため、指差呼称等を励行するよう指導を強化すること |
| 3 | 事業者は、墜落危険のある場所での作業がある場合には、応急の作業の場合でも、必ず昇降設備を設け、かつ、セフティブロックを設置すること |
| 4 | 事業者は、墜落の危険のある場所での作業を指示したときは、安全な作業方法で行わせ、確認し、作業員任せにしないこと。 |
| 5 | 事業者は、作業計画を明確に定め、作業打ち合わせで関係者に周知を図ること |
| 6 | 事業者は、作業員への安全教育を徹底して行うこと |
| 7 | 元請事業者は下請事業者を含む安全管理組織を確立し、現場の安全管理を徹底すること |
 厚生労働省
厚生労働省