荷とともにフォークリフトのパレットに搭乗した作業者が墜落
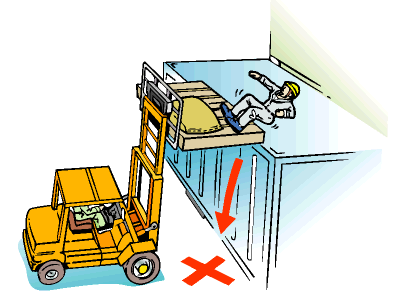
| 業種 | 陸上貨物取扱業 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業場規模 | 30〜99人 | |||||
| 機械設備・有害物質の種類(起因物) | フォークリフト | |||||
| 災害の種類(事故の型) | 墜落、転落 | |||||
| 被害者数 |
|
|||||
| 発生要因(物) | 防護・安全装置がない | |||||
| 発生要因(人) | 危険感覚 | |||||
| 発生要因(管理) | 機械、装置等を指定外の方法で使う | |||||
No.1128
発生状況
この災害は、他社のコンテナ積み卸し作業現場(コンテナヤード)で共同作業中に発生したものである。A社の班長は、午前中から貨物鉄道で到着したコンテナを最大荷重10トンのフォークリフトで構内に卸す作業を行っていたが、午後5時30分頃、同社のトラック運転手に「荷が一袋足りないので、上屋から持ってきてコンテナに入れてくれ」と指示した。
運転手は、上屋で荷を探したが、見当たらなかったので、「どこにあるか分からない」と班長に報告し、事務所へ引き揚げた。
被災者は、その状況を見聞きしていて、自分で上屋へ荷を探しに行き、破損していない袋を探し出し、袋をパレットに載せ、フォークリフトでコンテナ積込み場所まで運搬した。
次いで、被災者は、当日の運転日報を記録していた副班長に「コンテナの中へ荷物を1つ上げたいので、自分がパレットに乗るからフォークリフトを運転してほしい」と依頼し現場に向かった。
現場に到着後、被災者がパレットに乗り込み、副班長はフォークリフトの運転を開始した。
フォークを高さ2m50cmまで上昇させ、次いでコンテナの屋根にパレットを乗せようとしてフォークリフトを前進させたときに、被災者がパレット上から墜落した。
原因
この災害は、他社のコンテナ積卸し作業現場(コンテナヤード)で共同作業中に発生したものであるが、その原因としては次のことが考えられる。災害の直接の原因は、2段積みされたコンテナの上に被災者を運ぼうとして、フォークリフトの用途外使用をしたことである。
その背景としては、高い場所での作業が多いにもかかわらず、安全に昇降する設備等を設けていなかったことが挙げられる。
また、コンテナ屋根上の作業あるいは2段目のコンテナ内作業が、墜落防止措置が必要な高所作業であることの認識がなく、安全対策を行っていなかったことがあげられる。
さらに、被災者の所属していた会社は、大手運送会社の仕事を専属的に行っており、作業の場所も親会社の構内であり、作業指揮等についても親会社に依存していた。
なお、本社においては、安全管理者、衛生管理者、産業医の選任、安全衛生委員会の設置等一応の組織体制はあったものの、具体的な活動はほとんどなされておらず、コンテナ作業についてのマニュアル等も整備されていなかった。
対策
この災害は、コンテナ積卸し作業現場(コンテナヤード)で共同作業中に発生したものであるが、同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。| 1 親企業が主導する安全衛生管理 | |
| (1) 関係者で協議する協議会等を設置し、定期的に安全衛生に関する検討、協議を行う。 (2) 荷の積卸し場所での混在作業においては、事前の連絡・調整を確実に実施し、関係労働者全員に周知する。 | |
作業の指揮等が実態上親会社によって行われる場合であっても、必要な安全措置、安全教育について事業者の責任で実施する。
3 安全衛生教育の徹底
作業者に対して、取り扱う荷・作業の種類等に伴う危険有害性について安全衛生教育を行う。
4 作業マニュアル等の整備
使用機材、作業の手順、必要な安全対策等を含めた作業マニュアルを作成する。
5 昇降設備等の準備
専用のタラップ等安全な昇降設備をあらかじめ準備しておく。
6 職場巡視の実施
安全管理者の職務である作業場等の巡視を確実に実行する。
 厚生労働省
厚生労働省