魚加工工場の荷物用エレベーターの搬器と2階の床との間に挟まれる
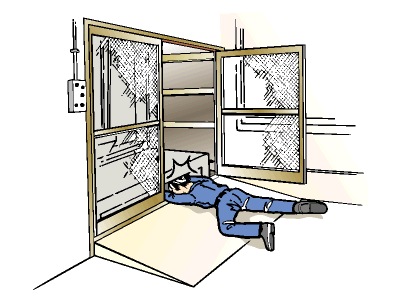
| 業種 | 水産食料品製造業 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業場規模 | 5〜15人 | |||||
| 機械設備・有害物質の種類(起因物) | エレベータ、リフト | |||||
| 災害の種類(事故の型) | はさまれ、巻き込まれ | |||||
| 被害者数 |
|
|||||
| 発生要因(物) | 設計不良 | |||||
| 発生要因(人) | 場面行動 | |||||
| 発生要因(管理) | 機械装置を不意に動かす | |||||
No.1045
発生状況
この災害は、魚の加工工場の荷物用エレベーターで発生したものである。この工場では、1階の作業場で魚を開いて塩付けを行い、それを、「せいろ」に一枚づつ並べ、それを工場2階に運び乾燥させ、製品として出荷している。
災害当日、工場では通常の作業が続けられていたが、途中で被災者の夫が腰痛を訴え、しばらくは我慢して作業を続けたものの、痛みがひどくなったので大事をとって午後2時頃早退した。
その後、社長の指示により、被災者が夫の行っていた作業を行い、運搬作業、乾燥作業も夫と同じ順序に従って行い、一連の作業も順調に3回終了した。
午後5時20分頃、被災者は、この日最後の作業となる運搬用の台車をエレベーターの搬器に載せて、2階へ上昇させるスイッチを入れたので台車は2階へ昇って行った。
しかし、何時もなら4〜5分でエレベーターが1階に降りてくるのに20分位経過してもエレベーターが1階へ降りてこないので、不審に思った社長の長女が2階へ行ったところ、エレベーターの昇降路の出入口の前でエレベーターの搬器の上部枠と2階床との間に頭部をはさまれ、うつ伏せに倒れている被災者を発見した。
原因
この災害は、魚の加工工場の荷物用エレベーターで発生したものであるが、その原因としては、次のことが考えられる。直接原因としては、
(1) 昇降路の1階の出入口に、戸が設けられていなったこと。
(2) 搬器の出入口に、戸が設けられていなかったこと。
(3) 昇降路の出入口の戸のすべてが閉じていないのに、搬器が昇降してしまう構造となっていたこと。
また、もう一つの原因としては、通常の業務としては実施していないエレベーターを不十分な知識、経験のまま操作し、結果的に昇降路の出入口の戸を開けたままエレベーターの運転操作したことがあげられる。
対策
この災害は、魚の加工工場の荷物用エレベーターで発生したものであるが、同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。1 安全管理体制の確立
一定の知識、経験を有する安全衛生推進者等を指名し具体的な活動の計画の策定等を行なわせる。
2 適正な機械設備の設置
機械設備の設計・設置の段階から必要な安全装置が具備されたものとする。
3 点検整備の実施
定期に或いはその日の作業開始前に点検し、必要な補修を実施する。
4 作業者に対する安全教育の実施
機械設備の操作にあたる者を指名するとともに、あらかじめ安全な使用のための教育を実施する。
 厚生労働省
厚生労働省