樹脂製品を旋盤加工中にはさまれて死亡
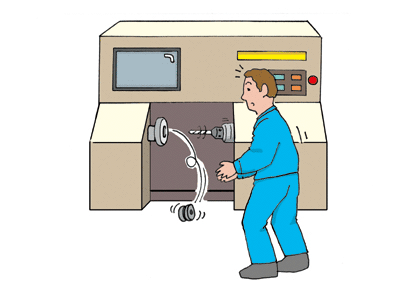
| 業種 | プラスチック製品製造業 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業場規模 | 5〜15人 | |||||
| 機械設備・有害物質の種類(起因物) | 一般動力機械 | |||||
| 災害の種類(事故の型) | はさまれ、巻き込まれ | |||||
| 被害者数 |
|
|||||
| 発生要因(物) | 防護・安全装置が不完全 | |||||
| 発生要因(人) | 危険感覚 | |||||
| 発生要因(管理) | 不意の危険に対する措置の不履行 | |||||
No.101057
発生状況
| この災害は、自動制御された旋盤で樹脂製品を加工しているときに発生したものである。 災害発生当日、作業者Aは、パートタイムの作業者Bと二人組で、自動制御された旋盤を使用した樹脂製品の切削加工の工程で材料の供給と加工された製品の取り出しを行っていた。 この切削加工は、材料を旋盤のチャックに手でセットしてから約2分で終了し、加工された樹脂製品は手で受け取って製品用ボックスに収納するという手順で行われていた。作業を始めて約2時間経過したとき、Aは加工された製品を手で受け取れずに下に落としてしまった。Aが落とした製品を拾おうとして上半身を屈めて旋盤の内部に手を伸ばしたところ、次の製品加工のため設定された加工位置まで移動してきたタレット(バイト等を装着するもの)とチャックとの間にはさまれた。これを見ていたBは、旋盤を停止することができなかったため大声で工場長を呼び、駆けつけた工場長が旋盤の自動運転を解除してAを救出したが、既に死亡していた。Aの作業位置から旋盤に取り付けられた非常停止スイッチは離れており、これを押すことは困難であった。 Aがはさまれた旋盤には、前面に柵が取り付けられており、切削加工中は柵を閉じ、材料の供給と製品の取り出しのときのみ柵を開けることにしていた。しかし、柵と旋盤がインターロックされていなかったこと、および製品1個の加工時間が約2分と短いことから、次第に柵を開放したまま切削加工が行われるようになっていた。なお、旋盤を使用する切削加工の方法や手順を盛り込んだ作業手順書は作成されていなかった。 また、旋盤に供給する部品や加工された製品を落としたときの措置手順や旋盤の自動制御の解除方法について、教育は実施されておらず、関係者業者に周知徹底されていなかった。 |
原因
| この災害の原因としては、次のようなことが考えられる。 | |
| 1 | 旋盤の安全措置が不十分であったこと 旋盤の前面には柵が取り付けられていたが、柵を開放しても旋盤はインターロックがないため運転されていた。さらに、旋盤に非常停止スイッチはあったものの、Aの作業位置からは離れており、操作することは困難であった。また、材料や製品が落下するおそれのある装置の構造であったことも一因である。 |
| 2 | 作業手順書が作成されていなかったこと 自動制御された旋盤を使用する切削加工について安全な作業方法を盛り込んだ作業手順書が作成されていなかった。 |
| 3 | 安全衛生教育を実施していなかったこと 旋盤に供給する部品や加工された製品を落としたときの措置手順や旋盤の自動制御の解除方法について関係作業者に教育されていなかった。そのため、Aは危険域に身を入れて落ちた製品を取ろうとし、また、BはAがはさまれるのを目撃したが、旋盤の自動制御を解除することができず、Aの救出が遅れた。 |
対策
| 同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。 | |
| 1 | 機械設備に必要な安全措置を講じること 旋盤等を使用した製品加工の作業では、リスクアセスメントを実施して作業に伴う危険有害性を評価し、必要な安全措置を講じることが必要である。 この事例の場合には、旋盤の前面に設けた柵を開放したときは旋盤が直ちに停止し、柵を開放中は決して動き出さないようにインターロックするとともに作業者の立ち位置から容易に操作できる位置に非常停止スイッチを設けるようにする。また、材料の供給や製品の搬出については、落下するおそれのない構造とする。 |
| 2 | 作業手順書を作成すること 自動制御される機械であっても、通常の操作の方法や手順のほか、異常発生時の措置、清掃、点検の方法等も盛り込んだ作業手順書を作成する。 |
| 3 | 安全衛生教育を実施すること 機械を使用して行う作業において、異常が発生したときの措置や自動制御の解除方法等も含めて、関係作業者に安全衛生教育を行う。 |
 厚生労働省
厚生労働省