石油精製プラントにおいて、ナフサが漏出して発火
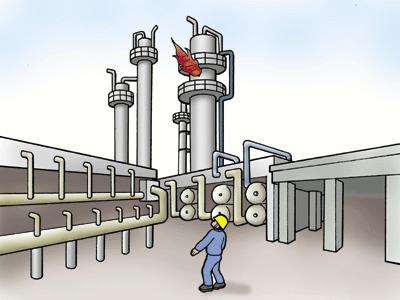
| 業種 | 石油製品・石炭製品製造業 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業場規模 | 100〜299人 | |||||
| 機械設備・有害物質の種類(起因物) | 可燃性のガス | |||||
| 災害の種類(事故の型) | 火災 | |||||
| 被害者数 |
|
|||||
| 発生要因(物) | ||||||
| 発生要因(人) | ||||||
| 発生要因(管理) | ||||||
No.100703
発生状況
この災害は、石油精製プラントにおいて、重質軽油水素化脱硫プラントで低圧分離された油からナフサ分を分離する脱硫放散塔から漏れ出したナフサが発火したものである。重質軽油水素化脱硫プラントでは、重質軽油と水素が合流後、熱交換器、加熱炉で加熱され水素化脱硫反応塔へ送られ、水素化処理された油を冷却し、高圧高温分離槽、低圧高温分離槽で水素、硫化水素、軽質炭化水素ガスに分離される。脱硫放散塔では、低圧分離槽で分離された油が送給されてナフサ分を分離して脱硫油を取り出すものである。重質軽油水素化脱硫プラントの定常運転中、脱硫放散塔は、温度が228℃、圧力が0.38Mpで運転されている。
火災が発生した日、構内下請の作業員が、定期修理の準備のため、重質軽油水素化脱硫プラントの熱交換器の近くで図面チェックをしていたところ、脱硫放散塔の頂部付近に位置する保温板金の15cm角の窓の隙間から50cmの炎が上がっているのを発見し、直ちにコントロールセンターに通報して、プラントの緊急遮断を行い消火した。
原因
この災害は、脱硫放散塔から漏れ出したナフサが発火したものであるが、その原因としては、次のようなことが考えられる。| 1 | 脱硫放散塔の頂部付近に開いた孔からナフサを主成分とする炭化水素が漏出したこと。 |
| 2 | ナフサが漏出した孔は、1年半前に肉盛り溶接により補修した箇所にあり、クラッド鋼の外側部分の炭素鋼溶融金属が内側部分のステンレス鋼溶融金属面から露出し、硫化水素などを含む腐食環境にさらされ、異種金属間の電位差による腐食が進行し、内部から減肉して開孔に至ったものと推定されること。 |
| 3 | 漏出したナフサが大気に放出されたとき、ナフサ留分の最低発火温度と定常運転状態の脱硫放散塔の温度条件がほぼ同温度であったこと。 |
| 4 | クラッド鋼の肉盛りによる補修要領の明確な基準が示されていなかったこと、補修後のチェックが十分に行われていなかったことなどにより、補修箇所の溶接施工不良が見過ごされ腐食を促進する結果を招いたこと。 |
| 5 | 補修時の基準の作成状況を確認する体制が十分に機能していなかったため、補修要領が作成されずに補修作業について作業員の判断に委ねられていたこと。 |
対策
この災害は、脱硫放散塔から漏れ出したナフサが発火したものであるが、同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要である。| 1 | 硫化水素などが存在する腐食環境にさらされる部分には、腐食し難い材質を使用すること。 |
| 2 | 部分的に腐食箇所を肉盛り溶接などで補修するときは、腐食状況および材質に応じた適切な補修が行われるように、補修の方法および補修後のチェック方法などの補修基準を定めて、この基準に基づく作業手順を作成し、補修を行うこと。 |
| 3 | 腐食などにより補修した箇所は、腐食の進行状況を確認するための点検方法および判定基準を作成し、適切な期間ごとに、継続して行われるように点検基準を見直すこと。 なお、点検は、単に、外観を目視によるものだけではなく、厚み計などの計測器を用いて行う必要があること。 |
| 4 | 腐食などにより補修が行われたときは、関連する補修基準、判定基準、点検基準および作業手順などの見直しが確実に行われるように、職制および安全衛生管理部門による責任と権限を明確にするための安全衛生管理体制の見直しを行うこと。 |
 厚生労働省
厚生労働省