鉄道車両の検収建屋の屋根葺き作業中、作業者が熱中症で倒れる
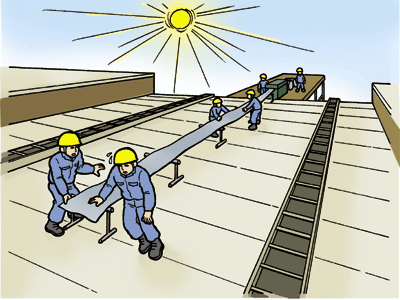
| 業種 | 鉄骨・鉄筋コンクリート造家屋建築工事業 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業場規模 | 5〜15人 | |||||
| 機械設備・有害物質の種類(起因物) | 高温・低温環境 | |||||
| 災害の種類(事故の型) | 高温・低温の物との接触 | |||||
| 建設業のみ | 工事の種類 | |||||
| 災害の種類 | ||||||
| 被害者数 |
|
|||||
| 発生要因(物) | 自然の危険 | |||||
| 発生要因(人) | 身体機能 | |||||
| 発生要因(管理) | 有害な場所に近づく | |||||
No.100535
発生状況
この災害は、鉄道車両の検収建屋の新築工事において、屋根葺き作業中の作業者が熱中症で倒れたものである。建屋(幅210m、奥行き150m、高さ6.5mの平屋)の屋根葺き作業は、構台の上に設置した成型機で幅50cm、高さ16cmに加工した厚さ0.8mmのロール状鋼板を必要に応じて定めた長さの屋根材をコロによって屋根上の所定の場所まで運搬するものである。
災害発生当日、作業者A他同僚2名は初めてこの現場に入り、作業開始前に、新規参入者教育、安全ミーティングを20分受けた後、午前8時40分に作業を開始した。Aの作業は、コロで送られてきた屋根材(長さ27m、重量130kg)を作業者数名で約20m移動させるもので、午前10時から30分、正午から1時間休憩を取り、作業が続行された。
午後2時30分頃、監督者BがAの足元がふらついているのを見て休憩するよう指示した。Bが30分後に様子を見に行って、Aに声を掛けても反応がなかったので、ワゴン車で病院に搬送したが、Aは8日後に死亡した。
Aの服装は安全帽に安全帯、長袖の作業服に運動靴を着用し、健康状態も良好であった。 当日は、最高気温28.3℃、晴天であった。
原因
この災害は、屋根葺き工事に従事していた作業者が熱中症で倒れた災害であるが、その原因としては、次のようなことが考えられる。| 1 | 作業場の気温が高かったこと 災害発生当日の当該地域の気温等は、消防署測定データによれば、最高気温28.3℃、平均気温20.1℃、最高相対湿度99.8%、平均湿度72.2%である。また、災害発生後に、測定した現場の最高気温は、晴天の日は地上で2〜3度、屋根上で4〜5度最高気温より高くなっている。このことから、災害発生時の屋根上の気温は34〜35℃と推定され、気温の高い環境の下で、作業を続けた。 |
| 2 | 監督者も、作業者も熱中症の予防に関して危険意識が乏しかったこと 監督者は夏季の屋外作業における熱中症の予防に関する一般的な知識はもっていたと考えられるが、熱中症が5月に発生するとは考えなかったと推定される。 また、被災者は建設労働の経験が浅く、熱中症に関する知識は乏しかった。 |
| 3 | 救急処置が不十分であったこと 被災者が倒れた後に、涼しいところで安静にして、水を取らせるなどしなかった。 |
対策
この災害は、鉄道車両の検収建屋新築工事で屋根葺きに従事していた作業者が熱中症で倒れたものであるが、同種災害の防止のためには、次のような対策の徹底が必要と考えられる。| 1 | 作業指揮者、作業者に熱中症の危険について、労働衛生教育を徹底すること 熱中症が屋外作業の多い建設現場で発生しているが、真夏ばかりでなく、5月の関東地方であっても起こることに注意する必要がある。 |
| 2 | 作業環境を正確に把握するため、気温、湿度等の作業環境測定を実施すること |
| 3 | 涼しい休憩場所を確保すること |
| 4 | 水分および塩分を準備し、補給を十分に行うこと 作業者が水分等を補給する時間の確保については、基準を明確化して、監督者に徹底させる必要がある。 |
| 5 | 熱中症の発生するおそれのある作業又は場所で作業を行う場合には、監督者は作業開始前および作業中に作業者の体調のチェックを実施すること 作業開始前の体調のチェックは作業者の自己申告に頼らず、監督者が作業者一人ひとりに対して行うことが大切である。 |
 厚生労働省
厚生労働省