下水管布設のための溝掘削工事における土砂崩壊
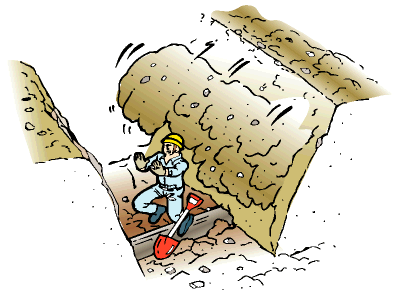
| 業種 | 上下水道工事業 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業場規模 | 5〜15人 | |||||
| 機械設備・有害物質の種類(起因物) | 地山、岩石 | |||||
| 災害の種類(事故の型) | 崩壊、倒壊 | |||||
| 建設業のみ | 工事の種類 | 上下水道工事 | ||||
| 災害の種類 | 土砂崩壊 | |||||
| 被害者数 |
|
|||||
| 発生要因(物) | 法面の欠陥 | |||||
| 発生要因(人) | 憶測判断 | |||||
| 発生要因(管理) | その他 | |||||
No.100052
発生状況
この災害は、下水管埋設工事のために行われた溝掘削作業において土砂が崩壊して発生したものである。当該工事は宅地造成工事の一部として行われ、既設の汚水本管(ヒューム管、直径250mm)に枝管(塩ビ管、直径150mm)を取り付けるものであった。枝管の布設のための溝の掘削にはドラグショベル(バケット0.1m2)が用いられた。当日の午後2時45分頃作業員が掘削穴(縦約3m、横約2m、深さ約2.7m)に立ち入って、管取り付けのために本管の土被りをシャベルで掘削していたところ、掘削壁面が縦2.5m、横1.3m、深さ2.7mの三角錘状に崩壊し生き埋めとなった。原因
この災害は、下水管埋設工事のために行われた溝掘削作業において土砂が崩壊して発生したものであるが、この災害の発生原因としては次のようなことが考えられる。1 地山がほぼ垂直に掘削されていたこと
2 土留め等の崩壊防止対策が講じられていなかったこと
3 掘削土により法肩の上載圧が増加したこと
4 ドラグショベルの作業振動が作用したこと
5 掘削作業主任者を選任していなかったこと
6 安全な作業計画が策定されていなかったこと
対策
この災害は、下水管埋設工事のために行われた溝掘削作業において土砂が崩壊して発生したものである。当該工事は宅地造成工事の一部として行われ、既設の汚水本管(ヒューム管、直径250mm)に枝管(塩ビ管、直径150mm)を取り付けるものであった。枝管の布設のための溝の掘削にはドラグショベル(バケット0.1m2)が用いられた。当日の午後2時45分頃作業員が掘削穴(縦約3m、横約2m、深さ約2.7m)に立ち入って、管取り付けのために本管の土被りをシャベルで掘削していたところ、掘削壁面が縦2.5m、横1.3m、深さ2.7mの三角錘状に崩壊し生き埋めとなった。同種災害の再発防止のためには、次のような対策の徹底が必要であると考えられる。1 掘削面を安全な勾配とすること
2 崩壊の危険性がある場合には崩壊防止措置を講じること
3 資格のある作業者主任者の直接指揮のもとに作業を行う
4 地山の事前調査を行って、作業方法を検討すること
5 安全管理体制を整備し安全衛生教育を実施すること
 厚生労働省
厚生労働省