タンクローリーの硝酸をトリエタノールアミンのタンクに誤って注入、タンクが破裂
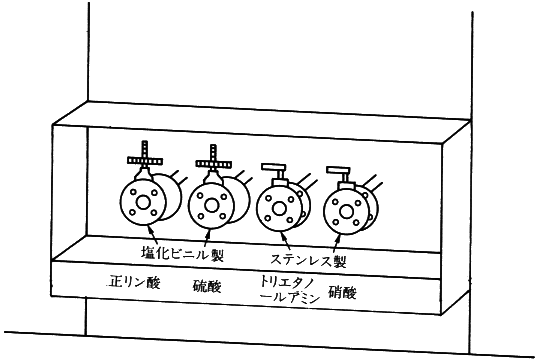
| 業種 | 電気機械器具製造業 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業場規模 | − | |||||
| 機械設備・有害物質の種類(起因物) | その他の危険物、有害物等 | |||||
| 災害の種類(事故の型) | 破裂 | |||||
| 被害者数 |
|
|||||
| 発生要因(物) | ||||||
| 発生要因(人) | ||||||
| 発生要因(管理) | ||||||
No.789
発生状況
本災害は、A社タンクヤード内の硝酸タンクに、タンクローリー車に積載してきた濃度65%の硝酸を注入することとなっていたが、タンクローリーのホースを誤ってトリエタノールアミン(以下「TEA」という)の注入口に接続したため、この硝酸がTEAタンク内に混入し、中和反応が起こり液温が上昇、また硝酸ガスが発生する等により、TEAタンクが破裂したものである。災害発生場所は、工場で使用する薬品類の貯蔵、希釈等の作業を行っている3階建て鉄骨コンクリート造りの工場1階部分のタンクヤードであり、当該タンクヤード東壁面にはタンクローリーで搬入される薬品の注入口が設置されている。
災害発生当日、硝酸の輸送を請け負っているB社の運転手Cが運転するタンクローリーが到着したのは、午後5時半ごろであった。
運転手Cは、当工場への搬入は初めてであり、出発時に、タンクローリーのホースの注入口は、4カ所ある注入口の左から2番目であると教わっていた。しかし、その注入口が塩化ビニル製であったため硝酸の注入口はステンレス製でできているものと判断し、右から2番目のステンレス製の注入口にホースを接続した。
A社の薬品受け入れ担当のDは、硝酸タンクの受け入れ電磁弁を開け、Cに注入を指示した。Cは、硝酸タンクの液面計を見たところレベルが上昇せず、TEAタンクの液面計のレベルが上昇していたので、あわててDに連絡し、ホースを外し、配管内部に残留している硝酸を排出した。
Cは、Dに「TEAタンクに硝酸が入ったが大丈夫か」と確認したところ、Dは、TEAタンクの電磁弁を開けていないので、硝酸は入っていないものと判断し、右端の硝酸の注入口にホースをつなぎ直させ、硝酸の注入を再開させた。
ところで、TEAタンクの電磁弁は開けていなかったが、TEAタンク配管の清掃作業により、バイパス配管の手動バルブが開けたままとなっており、先の誤った注入作業により相当量の硝酸がTEAタンクに混入し、TEAタンク(直径50cm、高さ90cm、ステンレス製円筒形型)が破裂したものである。
原因
| (1) TEAタンク注入口に誤って硝酸のホースを接続し、TEAタンク内に硝酸を注入したことについて、 | |
| イ 特定化学物質等作業主任者が、硝酸の受入れ作業に立ち会わず、直接の作業指揮をしていなかったこと。 ロ 工場側受け入れ担当者の薬品受入れ時の業務は、納品伝票の確認、電磁弁の確認、タンク内薬品の残量確認であり、ホースの注入口の接続の確認については、搬入業者に任せていたこと。 ハ 硝酸搬入業者のタンクローリー運転手は、当該工場に来るのが初めてであり、また、誤った注入口を教えられていたこと。 ニ 4カ所の薬品注入口について、いずれも形状が同じであり、区別がつかないこと。また、薬品名の表示は、小さく消えかけており、不明であったこと。搬入の時間が夕刻で暗かったにもかかわらず、照明設備がなかったこと。 ホ 混合により激しい中和反応を起こす酸とアルカリの注入口を並べて設置していたこと。 | |
| (2) TEAタンクのバイパス配管の手動バルブが開けられていたことについて、 | |
| イ 手動バルブを開けた作業者と、薬品受け入れ担当者との連携が図られていなかったこと。 ロ 薬品注入口からは、手動バルブの開閉状況を確認できる状況となっていなかったこと。 | |
対策
| (1) 特定化学物質等作業主任者に、硝酸の受入れ作業に立ち会わせ、直接作業指揮をさせること。 (2) 工場側受入れ担当者および硝酸等搬入業者のタンクローリー運転手に対して、薬品の性状、危険性、取扱い上の注意、安全作業方法、緊急時の措置等について、十分な安全衛生教育を実施すること。 (3) 誤った注入を避けるために、 |
| イ 薬品ごとにフランジの形状を変え、かつ、注入口に薬品名を明確に表示すること。 ロ 注入口付近に照明を取り付け、夜間でも表示が確認できるようにすること。 ハ 混入すると急激な反応を起こす酸とアルカリ等の注入口は、近接した位置に設置しないこと。 ニ 手動バルブを開けているときは、表示札等により表示する。 | |
| (4) 誤った注入が行われた場合の対処方法について具体的に定め、当該訓練を実施すること。 | |
 厚生労働省
厚生労働省