マンホール内における酸素欠乏症
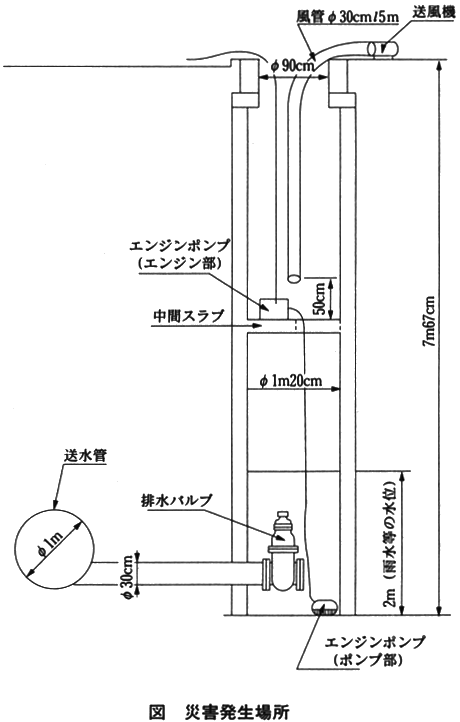
| 業種 | 土地整理土木工事業 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 事業場規模 | − | |||||
| 機械設備・有害物質の種類(起因物) | 異常環境等 | |||||
| 災害の種類(事故の型) | 有害物等との接触 | |||||
| 建設業のみ | 工事の種類 | その他の土木工事 | ||||
| 災害の種類 | 酸欠 | |||||
| 被害者数 |
|
|||||
| 発生要因(物) | ||||||
| 発生要因(人) | ||||||
| 発生要因(管理) | ||||||
No.862
発生状況
災害発生当日の被災者の作業内容は、マンホール内を清掃するため、ポンプ(ガソリンエンジンを動力として用いるもの)を用いて内部にたまった雨水等(排水室底部より2m程度)を排水する作業であった。被災者は14時40分ごろ、作業者Aと2人で送風機により当該マンホールの換気を開始するとともに、ポンプを起動し排水作業を開始した。1時間30分後、ポンプと送風機を停止し、両方とも地上に引き上げた。5分後、再度送風機により15分間換気を行った後、被災者がマンホール内で手作業により室底部に残った雨水等をくみ上げ始めた。20分後、作業者Aが地上より被災者を呼んだが、返事がなかったのでマンホール内に入ったところ、意識を失っている被災者を発見した(この時、マンホール内に残っていた雨水等は底部より5cm程度となっていた)。作業者Aは事務所に連絡をするとともに、事務所に備え付けてあった携帯用缶入り濃縮酸素を被災者に吸わせ、救急隊が来るまでその場で待機した。救急隊により病院に運ばれ診断を受けたところ、低酸素脳症で3日間の休業と診断された。
災害発生後、現場を調査したところ、マンホール底部から50cmの所での酸素濃度は通常の空気より低い18.7%であった。被災者にはさらに低い濃度と推定された。マンホール内には雨水等が1カ月以上滞留しており、季節が夏ということもあり、連日の暑さにより雨水等に含まれる有機物が腐敗し、酸素が消費され、酸素欠乏空気が発生したと考えられる。
原因
[1] 雨水の長期間の滞留により雨水等が腐敗し、空気中の酸素が消費されたこと。[2] 送風機の風管が短く、酸素濃度が18%以上に保たれるよう、十分な換気が行われていなかったこと。
[3] マンホールに入る前にマンホール内の酸素の濃度を測定していなかったこと。
[4] 上記[2]、[3]などの酸素欠乏による危険を防止するための作業を指揮・管理する者がいなかったこと。
対策
[1] 第1種または第2種酸素欠乏危険作業主任者技能講習を修了した者のうちから、酸素欠乏危険作業主任者を選任し、所定の職務を行わせること。[2] 酸素欠乏危険作業に従事する作業者に対し、酸素欠乏の発生の原因、酸素欠乏症を防止するための対策等について、特別教育を行うこと。
[3] 作業を開始する前に、当該作業場所の酸素の濃度を測定させること。
[4] 空気中の酸素濃度を18%以上に保つように必要な換気を行うこと。
[5] 非常の場合に、作業者を救出するために必要な空気呼吸器等の避難用具を必要数備え、容易に利用できるようにすること。
 厚生労働省
厚生労働省